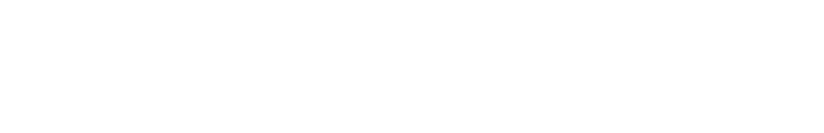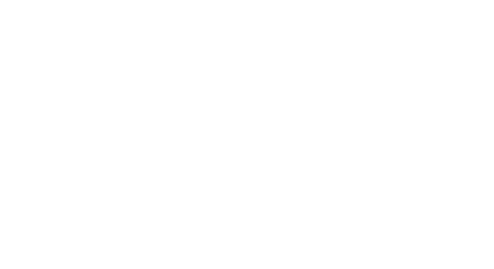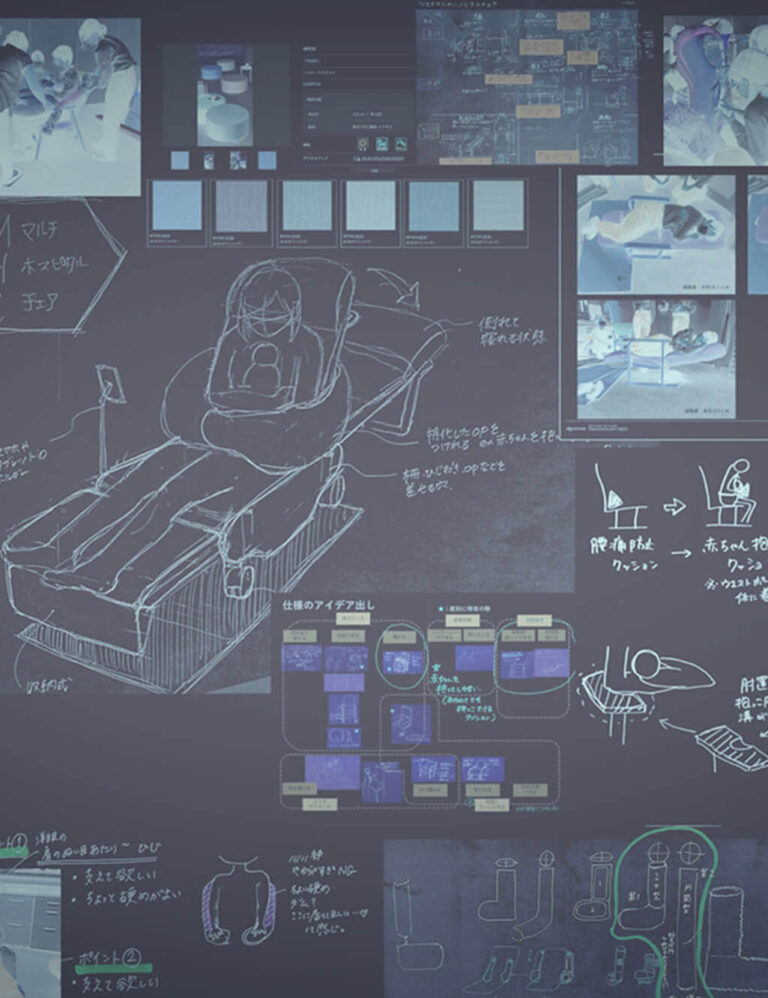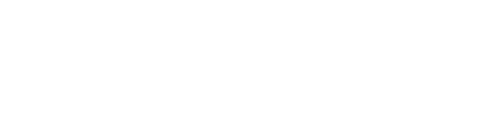パラマウントベッドが取り組む「WELL-BEING」。今度は社員が生徒にプレゼンテーション
歴史コーナーでパラマウントベッドの歩みを見学した後は再びセミナールームに戻り、今度は社員から長橋中学の生徒たちへ「パラマウントベッドが取り組む『WELL-BEING』」についての講話が行われました。
トップバッターは入社1年目の広報部中村さん。
4月に入社してまだ1ヶ月と少し(この職場訪問は5月21日)。生徒に一番年が近いこともあり、自己紹介や趣味の話から和んだ雰囲気で話はスタート。
「こういう私が、プライベートと仕事を両立させられるような会社はどこだろう?」
と、自身のストーリーを絡めてパラマウントベッドの紹介に移り、そこから自社が取り組む福利厚生など、従業員のWELL-BEINGを支える施策について、実例を交えて話しました。等身大の話から、そんな自分がどう会社と関わっていくのか、あるいは会社が一人ひとりのことをどう考えどうサポートしているのか、と展開する内容で、「社会に出て働くのはずっと先」という印象を持っていた中学生たちにとって、自分だったらどうだろう?と想像しやすいプレゼンテーションだったのではないでしょうか。
続いては同じく広報部の高橋さんの講話。
高橋さんはもう少し視点を広げて、企業としての姿勢やその背景を中心とした話でした。
なぜパラマウントベッドがWELL-BEINGに取り組んでいるのか、それが従業員個人や会社や、あるいは社会全体にとってどういう意味を持つのか。
企業と社会の関係という少し難しいテーマでしたが、講話の直前のショールーム案内で高橋さんが生徒たちと話していた、“事業拡大の歴史 = 使う人(ユーザー)の広がり = 「想う」対象の広がり” という内容とリンクしていて、彼らにとっては「あ、さっきの話だ」と、受け止めやすい雰囲気でした。
そして、WELL-BEINGに取り組む姿勢や背景の説明や企業としての様々な取り組みの紹介のあと、最後に「社員一人ひとりがWELL-BEING for 〜 を届けたい相手を考える」という一人ひとりの話として講話を締めくくりました。
中村さん、高橋さん、どちらのプレゼンテーションにも共通していたのは
・「自分のWELL-BEING for 〜」をぜひ探し続けて欲しい
・ 今日の体験や話が、そのきっかけやヒントになってくれれば嬉しい
という想いでした。





ふたたびショールームへ。今度は製品を実体験!
続いて、全員で本社2階のショールームに移動し、今度は様々なパラマウントベッドの製品を実際に体験しました。医療介護ベッドやサニタリー記録システムの実際の製品、また「眠りCONNECT」といった見守り支援システムのモニターを前に、機能や使い方の説明を受け、興味津々な生徒たち。
「じゃあ実際に操作してみる?」
「誰か、ベッドに寝て体験してみましょうか」
社員の呼びかけで実体験する生徒たち。
「このデザインにはこういう意味があるんだよ」とか「この機能はこういう目的で備わってるんです」という説明を受けると、途中からは自分たちだけで考えたり工夫をしながら製品を体験していました。

実際にベッドに横たわり、高さや角度を変えて体験。
医療を受ける側へのケアはもちろんのこと、医療スタッフに対しての配慮や工夫なども学ぶ


いいタイミングで「実はこういう目的でこの機能があるんですよ」と踏み込んだ説明をする広報部江さん
中学生だとあまり医療用ベッドや介護現場のモニタリングシステムには馴染みがないかもしれません。
でも彼ら自身で役割を交代しながら製品の体験をすることで、機能やデザインに込められた想いを感じとっている様子でした。
(後編「ちゃんと休んでも問題なく仕事が終わりますか?」へつづく)